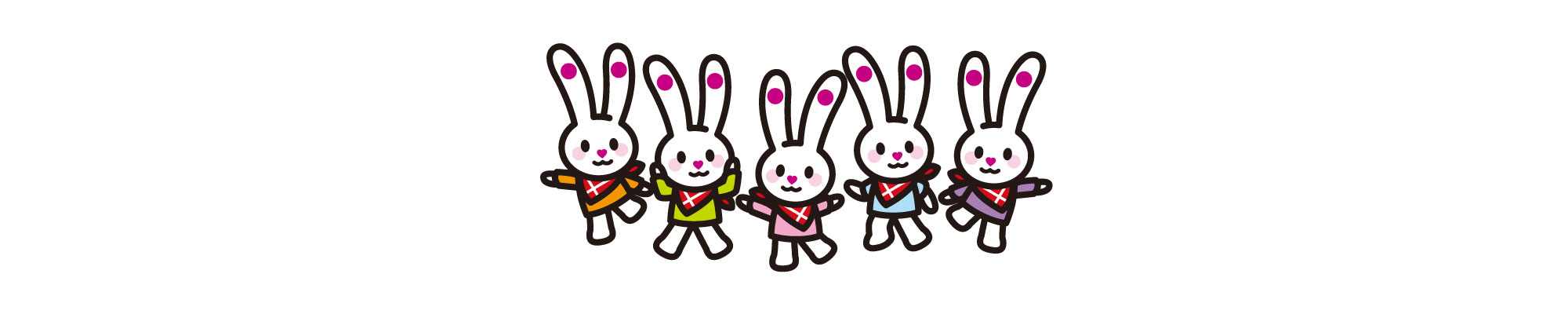花火の音が遅れて聞こえる、夜に遠くから列車の音が聞こえてくる、夜に海の波音が大きく感じる…日常の中に少し注意をむけると、ふだんは当たり前に受け入れていることでも、よく考えてみると理由がわからない、不思議ということは多いのではないでしょうか。その理由を追究するというよりも感性でうけとめれば、そこから文学的な発想につながるわけですが、今回はあえて理由を科学的に追究してみることにしましょう。あなたは理由がはっきりしてスッキリするタイプ?それとも逆に興ざめするタイプ?
今年もコロナウイルスの影響で、日本各地で多くの花火大会が中止になっています。
もともと花火大会の元祖と言われる隅田川の花火大会は、享保年間にコレラが蔓延した際、厄除けの意味を込めて1732年に暴れん坊将軍こと徳川吉宗が始めたものなので、疫病退散の意味もあるのですが、それさえ許されない状況になっているのです。
***
打ち上げ花火を見ていると、夜空にピカッと広がってしばらくしてからド~ンという音が響きます。
光は1秒間に約30万km進みますが、それに対して音は1秒間に約340mしか進みません。その伝達速度の違いによって光と音のズレが発生するのです。
花火が光ってから1秒ほど遅れて音が響く場合、光は一瞬で届くと考えると花火の高さは約340mの上空にあると考えることが出来ます。2秒なら約680m。これは雷でも同じ計算が出来ます。
***
そのように自然界にある光や音の速度は数値化されているのですが、実際には状況によってその速度は変わってきます。
音は空気中に発生した振動が伝達されて生じるものですが、空気の圧力や温度によって伝達速度が変化し、空気が暖かいと音は早く伝わるとされています。
そう言う意味では夏の暑い夜でも昼間よりは空気が冷えているので、花火大会の時刻には音がゆっくり伝わる事になります。
***

さらに音は温度の低い方に向かって屈折するという性格があります。これが昼間は聞こえなかった音が、夜になると聞こえるという変化をもたらします。
昼間は地表が太陽光で熱せられているため、音は空気温度の低い上空に向かって逃げていくのですが、夜になると音は空に向かわず地表近くを沿って進むようになります。
これが「夜中になると、遥か遠く離れた場所を走る鉄道の音が聞こえる」という現象を起こすのです。ふと真夜中に郷愁を誘うような現象もちゃんと科学的に証明出来るのです。
***
千年以上前に紫式部の書いた『源氏物語』の中では、都から遠く離れた兵庫県須磨に隠遁した光源氏が夜、海辺から離れた山中の庵で「夜寝ていると波の音が近くに聞こえてきて眠れない」と嘆く場面が出て来ます。
淋しさを際立たせる心理描写として秀逸な場面ですが、これにも科学的な理由がちゃんとあります。
地表以上に海水温は太陽光の影響を受けるため、真夜中の波の音はより近くに聞こえてしまうのです。
***
ちなみにアニメ『アルプスの少女ハイジ』の主題歌で「口笛はなぜ遠くまで聞こえるの?」(「おしえて」伊集加代子&ネリー・シュワルツ、コロムビア、1974)という歌詞がありますが、これは温度による変化は関係していません。ビルなど音を遮る物がないアルプスの山岳地帯だということもありますが、口笛の「ド」から1オクターブ高い「ド」は1KHz~2KHzの音で、人間の声より遠くへ響きやすいという性質を持っているからだと考えられます。さらに考察すると、ハイジ達の住んでいたスイス・オクセンベルクの高地は標高1100m地帯で若干空気圧が低いということも影響しているかも知れません。
ついでに続きの歌詞「あの雲はなぜ私を待ってるの?」は、ビルなど距離を測れるようなものが無い山岳地帯では、遠近の距離感が掴めず雲がすべて同じ距離にあるように見えることによる錯覚です。近い雲が早く流れた時、遠くにある雲が止まって見える錯覚が起き「あの雲がずっと止まって私を待っている」と思いこんでしまう原因になるのです。
***
このように自然界にある様々な現象もこうやって科学的に考えることができますが、それが想像の広がりを壊してしまうことにもなりかねないので、お子さんに教えていいものかどうか悩み所です。
-
記事投稿者

杉村 喜光(知泉)
雑学ライターとして、三省堂『異名・ニックネーム辞典』、ポプラ社『モノのなまえ事典』など著作多数。それ以外に様々な分野で活動。静岡のラジオで10年雑学を語りテレビ出演もあるが、ドラマ『ショムニ』主題歌の作詞なども手がける。現在は『源氏物語』の完訳漫画を手がけている。 2022年6月15日に最新巻『まだまだあった!! アレにもコレにも! モノのなまえ事典/ポプラ社』が発刊。