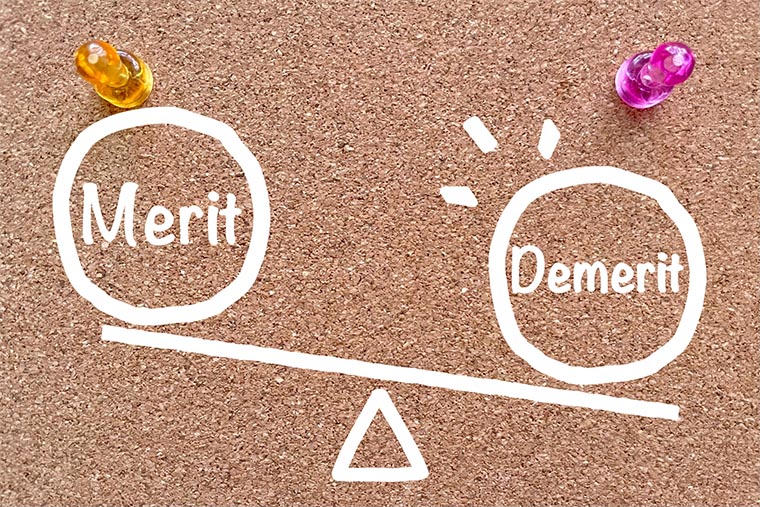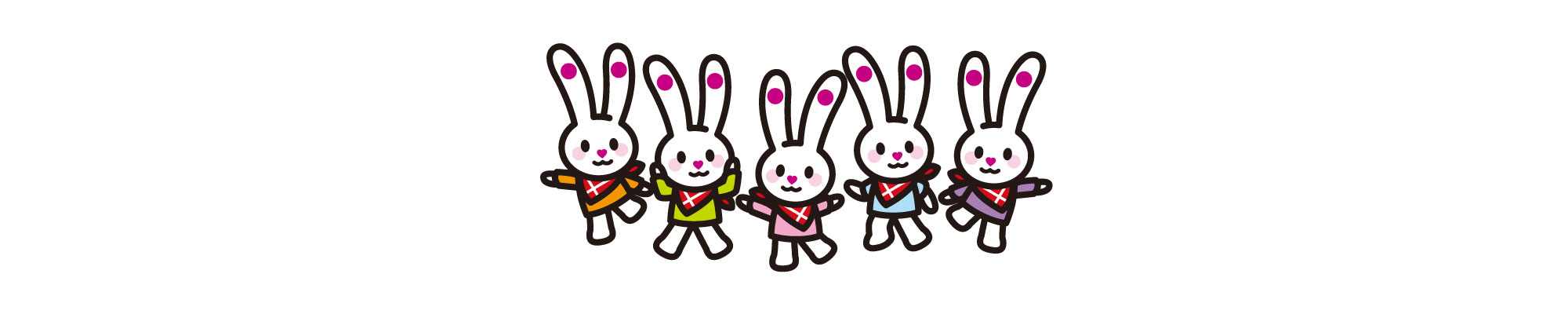「補聴器を買うにはどうすればよいの?」
「耳鼻科に行かないとダメ?」
このような悩みを抱えていませんか。補聴器の正しい買い方がわからず、購入に至っていない方もいるでしょう。補聴器は日々の生活の快適性に直結するため、使用目的や生活環境に合ったものを購入しなければなりません。
本記事では補聴器の買い方の流れを中心に下記の4つを解説します。
- 買い方を知る前におさえたい3つのポイント
- お求めやすく入手する方法
- 購入における5つの注意点
- 購入に関する3つの疑問
補聴器の公的補助制度についても解説しているため、お求めやすく入手する方法について知りたい方は参考にしてください。
補聴器の買い方を知る前におさえたい3つのポイント
補聴器の買い方を知る前に、下記のようなおさえたい3つのポイントがあります。
- 購入前に耳鼻咽喉科を受診する
- 信頼できる購入先を選ぶ
- 補聴器の使用目的や生活環境を把握する
それぞれの詳細を解説します。
1.購入前に耳鼻咽喉科を受診する
補聴器を購入する前に耳鼻咽喉科に受診するべき理由は下記の通りです。
- 聴力低下の原因が明確になり本当に補聴器が必要か判断できる
- 医師の診断を受けることで、補聴器が医療費控除や補助金制度の対象となる場合がある
適切な治療で聴力が改善して、補聴器が不要になるケースもあります。補聴器が必要と判断された場合は、どのような補聴器が良いか医師から助言を受けることも大切です。
より適切なサポートを受けたい場合は、補聴器相談医の認定を受けた医師の診察を受けることを推奨します。補聴器相談医とは、難聴の診察から補聴器の必要性の判断、補聴器の選択などをサポートしてくれる医師のこと。
「補聴器が本当に必要であるのか」「治療できる難聴であるのか」を判断するためにも、まずは耳鼻咽喉科を受診しましょう。
2.信頼できる補聴器専門店・取扱店を選ぶ
信頼できる購入先を選ぶことは重要です。購入先により、販売者の知識やサポート体制が異なるためです。
補聴器専門店・取扱店は定期的な補聴器の調整やクリーニングなど、さまざまなサービスを提供しています。特に下記のような購入先を推奨します。
| 認定補聴器専門店 | 公益財団法人テクノエイド協会により認定された補聴器専門店。下記のような運営基準が満たされている。 ・相談への対応 ・補聴器の調整の対応 ・認定補聴器技能者の常勤 ・補聴器相談医との連携 など |
|---|---|
| 認定補聴器技能者が在籍している補聴器専門店・取扱店 | 使用目的や予算に応じた補聴器の選択、調整、アドバイスなどが適切に行えるスタッフが在籍している |
自分に合った補聴器を購入するには、適切なアドバイスを受けることが大切。認定を受けている取扱店や専門の知識・技能をもつスタッフが在籍する購入先を選びましょう。
3.補聴器の使用目的や生活環境を把握する
補聴器を選ぶ際には、使用目的や生活環境を明確にすることが重要です。 補聴器の種類や機能を使用目的に合わせる必要があるためです。
使用目的の一例は下記の通りです。
- 静かな環境で家族や友人とのコミュニケーションを楽しみたい
- 仕事や趣味で利用するため複数人との会話の聞こえをよくしたい
他にもスマホと連動させて、音楽を聴きたい、ハンズフリーで通話したい、TVの音を直接聞きたい*、固定電話の通話時に、直接補聴器で音声を聞きたい*、という場合にはBluetooth内蔵だと便利です。使用感の良さと効果の実感を高めるためにも、使用目的と生活環境を明確にしましょう。
*別途オプション製品が必要です。補聴器の買い方6ステップ

補聴器の買い方6ステップは下記の通りです。
- 耳鼻咽喉科を受診する
- 補聴器取扱店でカウンセリングを受ける
- 補聴器の器種を選ぶ
- 補聴器のフィッティングを受ける
- 補聴器の試聴をする
- 補聴器を購入する
ここでは、補聴器相談医による診察や認定補聴器専門店でカウンセリングを受けることを前提に解説します。
1.耳鼻咽喉科を受診する
前述した通り聞こえに不調を感じたら、まずは耳鼻咽喉科を受診しましょう。耳鼻咽喉科を受診すると、難聴の有無を判断するために下記を実施します。
- 耳の診察
- 聴覚機能検査
- 難聴の診断
上記を実施することで、難聴の種類や原因、治療できるかなどが明確になり、補聴器が必要か判断できます。販売店での補聴器の選択をスムーズにするためにも、補聴器相談医から「補聴器適合に関する診療情報提供書」を受け取りましょう。
「補聴器適合に関する診療情報提供書」と補聴器購入の領収書があれば、医療費控除対象として申請が可能になります。なお、この書類は補聴器相談医にしか記入できないため注意してください。
2.補聴器専門店・取扱店でカウンセリングを受ける
耳鼻咽喉科を受診後、認定補聴器技能者が在籍する補聴器専門店・取扱店でカウンセリングを受けます。 担当者に「補聴器適合に関する診療情報提供書」を渡したあとに、日常生活で困っていることや補聴器に関する疑問などの話し合いが行われます。
カウンセリングをスムーズにするためにも下記を明確にしておきましょう。
本人の難聴の程度により、カウンセリングがスムーズに進まない可能性があります。家族と一緒にカウンセリングを受けましょう。
3.補聴器の機種を選ぶ
次に担当者と相談しながら補聴器の機種を選びます。 補聴器の種類は大きく分けると下記の通りです。
| タイプ | 特徴 | 値段 |
|---|---|---|
| 耳かけ型 | 耳にかけるタイプ。耳あな型と比較すると操作性が良い。小さくおしゃれなデザインが増えている。 | 5〜70万(片耳) |
| 耳あな型 | 耳のあなに収まるタイプ。小型で目立ちにくい。耳の形や聞こえの状況に合わせたオーダーメイドが一般的。 | 10〜70万(片耳) |
| ポケット型 | イヤホンと本体をコードでつなげるタイプ。操作性がよい。両耳で使用するには別途両耳用イヤホンが必要。 | 3〜12万 |
使用目的やフィット感が合っていないとストレスの原因となり、補聴器を使わなくなってしまう可能性もあります。
見た目やデザインだけで選ぶのは控えて、自分の使用目的やフィット感に合った補聴器を選択しましょう。
4.補聴器のフィッティングを受ける
購入する補聴器の候補が決まったらフィッティングを実施します。フィッティングとは、利用者に合う補聴器を選んで適切な状態に調整することです。
フィッティングの過程の一例は下記の通りです。
- 利用者に合った補聴器の初期設定を行う
- 補聴器を装用して聞こえの評価をする
- 聞こえの状況に応じて調整を実施する
状況にもよりますが上記の過程を実施し、1~2週間ほど試聴します。場合によっては補聴器の選択に戻ることもあります。補聴器や聞こえに関する疑問が芽生えた場合は、遠慮なく相談しましょう。
5.補聴器の試聴をする
試聴はフィッティングの過程の一つです。補聴器購入の際は十分な試聴が必要で、特に下記を確認してください。
- 会話を聞き分けることができるか
- 聞こえる声や周囲の音がうるさすぎないか
補聴器の使い心地は、ライフスタイルの快適性に直結します。可能であればレンタルサービスを利用して、日常生活で装用してみることを推奨します。
レンタル中は、実際の生活環境で要望通りの聞こえであるか何度も確認しましょう。補聴器の操作性や電池の出し入れなども、問題なくできるか確認してください。
6.補聴器を購入する
フィッティングを十分に実施したら補聴器を購入します。 購入の前に、下記のような保証やアフターサービスの内容を確認してください。
- 故障や紛失保証は充実しているか
- 聞こえの調整は随時行ってくれるか
- 点検や掃除などの対応をしてくれるか
製品が手元に届くまでの期間は、当日から1週間ほどで、補聴器のタイプにより異なります。お近くの補聴器販売店がわからない方は、下記の検索サービスをご利用ください。
補聴器をお求めやすく入手する方法|活用できる3つの公的補助制度

補聴器をお求めやすく入手する方法には、下記のような公的補助制度を利用する方法があります。
- 補装具費支給制度:自己負担を原則1割にできる
- 医療費控除:補聴器購入者が控除を受けられる
- 地方自治体の補助金:高齢者を対象にした支援などがある
それぞれの詳細を解説します。
1.補装具費支給制度|自己負担を原則1割にできる
補装具費支給制度とは、難聴により身体障害者手帳の交付を受けた方が、補聴器の利用者負担を原則1割にできる制度です。難聴の身体障害者の要件は下記の通りです。
- 両耳の聴力レベルが70デシベル以上
- 片耳の聴力レベルが90デシベル以上、もう一方の聴力レベルが50デシベル以上
- 両耳による言葉の聞き取りの正解率が50%以下
身体障害者手帳の交付申請は管轄の市町村で実施します。身体障害者手帳交付申請書や指定されている診断書・意見書などが必要であるため、購入前に福祉窓口に問い合わせましょう。
参考:厚生労働省 補装具費支給制度の概要2.医療費控除|補聴器購入者が控除を受けられる
補聴器は、医師に必要と診断された場合に医療費控除の対象となります。対象となるための流れは下記の通りです。
- 補聴器相談医に「補聴器適合に関する診療情報提供書」を記入してもらい、認定補聴器専門店に持っていく
- 補聴器購入後に「補聴器適合に関する診療情報提供書」の写しと領収書を受け取る
確定申告を忘れずに実施してください。なお、認定補聴器専門店または認定補聴器技能者以外から補聴器を購入した場合は、対象にならないため注意しましょう。
3.地方自治体の補助金|高齢者を対象にした支援などがある
地方自治体では、高齢者を対象にした補聴器購入費の補助制度などを設けています。例えば「難聴高齢者補聴器購入助成」というような、65歳以上の高齢者を対象とした補助金を給付している自治体が多数あります。
要件や申請の流れは各自治体によって異なる場合があるため、気になる方は管轄の福祉窓口に問い合わせてみましょう。
◆関連記事:国内での補聴器購入費用助成の地域格差
補聴器購入における5つの注意点

補聴器購入における5つの注意点は下記の通りです。
- 慣れるまでには3ヵ月は必要である
- 補聴器の値段が片耳表記でないかを確認する
- 高額な値段設定の補聴器が聞こえやすいとは限らない
- 補聴器本体は非課税、関連製品は課税される
- 返品対応が可能であるかを確認する
それぞれの詳細を解説します。
1.慣れるまでには3ヵ月は必要である
補聴器は購入後に調整が必要なことが一般的で、利用に慣れるまでには3ヵ月ほどの期間が必要です。主に下記のようなことを微調整していきます。
- 聞き取りにくい音を大きくする調整
- 騒音や音の響きを抑制する調整
- 会話がはっきり聞き取れるようにする調整
上記を1週間に1回のペースで最低でも3回ほど繰り返します。最初の3ヵ月は特にトラブルがなくても調整することが大切です。その後は聴力の変化もあるため、3〜6ヵ月に1回は調整しましょう。
2.補聴器の値段が片耳表記でないかを確認する
補聴器の価格表示は片耳分である場合が多いです。カタログには「片耳価格」「両耳価格」などのように値段が記載されているため注意してください。両耳に装用予定の方は、2つ分の予算が必要であるため間違えずに確認しましょう。
3.高額な値段設定の補聴器が聞こえやすいとは限らない
補聴器は高くても聞こえやすいとは限りません。高額な補聴器は性能や機能が充実している傾向にありますが、本人にとっての聞こえやすさはまた別です。
利用用途の無い機能により高額となっている可能性もあります。補聴器の選び方は、利用目的や生活環境に合わせることが大切です。担当者のアドバイスを受けながら、聞こえやすさや利用目的に合った補聴器を選択しましょう。
4.補聴器本体は非課税、関連製品は課税される
補聴器は身体障害者用物品であるため非課税とされています。しかし、下記のような関連製品は課税対象であるため注意してください。
- 補聴器用の電池
- 乾燥ケース
- クリーニングシート
事前に販売店で詳細を確認して、総合的な出費を把握して購入しましょう。
5.返品対応が可能であるかを確認する
補聴器の購入先が返品可能であるかを確認しましょう。補聴器購入後に「使ってみると合わなかった」「装着感が不快だった」「雑音がひどい」などのトラブルが起きる可能性もあるためです。
返品には「購入から◯日以内」のような条件が定められていることが一般的です。販売先で返品対応が設けられているかを条件とともに必ず確認してください。
補聴器の購入に関する3つの疑問
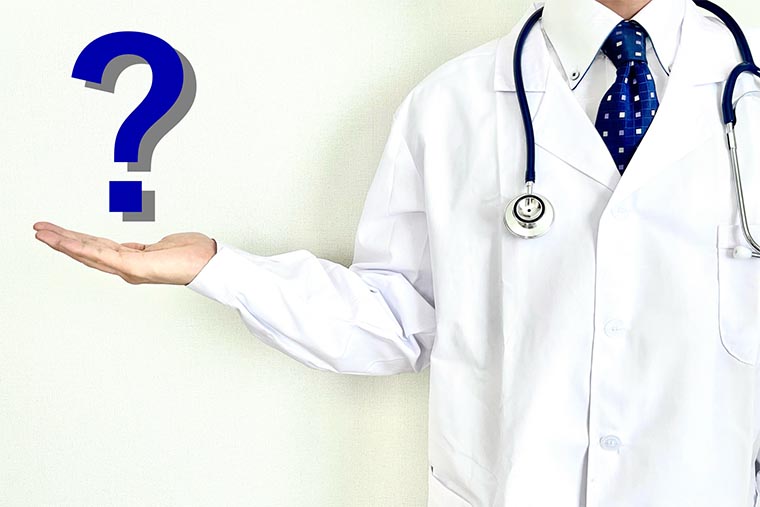
ここでは、下記の補聴器の購入に関する3つの疑問を解説します。
- 補聴器をつける基準は?
- 結局どこで買うのが良い?
- 補聴器は両耳のほうが良い?
購入前の疑問の解決に役立ててください。
1.補聴器をつける基準は?
聴力器を装着する基準は、聴力低下が日常生活に支障をきたし始めたときです。例えば下記の通りです。
- 会話で聞き返しが多くなった
- 数人での会話が聞き取りにくくなった
- 話し声が大きいと言われるようになった
- 車の接近に気づかなかった
- 耳鳴りがする
いくつか当てはまる場合は、まず耳鼻咽喉科に相談してみましょう。
2.結局どこで買うのが良い?
推奨される補聴器の購入先の一例を挙げると下記の通りです。
- 専門知識に基づいて相談や調整をしてくれる
- 補聴器相談医と連携している
- 購入後の調整やトラブルに対応してくれる
- 本人と家族が通いやすい距離にある
- 返品対応をしている
- 購入前のレンタルを実施している
認定補聴器専門店であれば、上記の1〜3は基本的に満たされています。購入先に迷ったら認定補聴器専門店を基準に考えましょう。
3.補聴器は両耳のほうが良い?
補聴器は可能であれば両耳装用を推奨します。理由は下記の通りです。
- 音が自然に聞こえる
- 音の位置や方向がわかりやすい
- 雑音の中でも会話が聞こえやすい
ただし、聴力の程度や耳の病気によっては、両耳装用をしても効果が得られないこともあります。事前に医師に両耳装用にしてもよいか確認しましょう。
補聴器の正しい買い方は信頼できる耳鼻咽喉科と補聴器専門店・取扱店を利用すること

自分に最適な補聴器を購入するためには、信頼できる耳鼻咽喉科と販売店を利用することが大切です。
受診先や販売先選びに迷ったら、補聴器相談医が在籍している医療機関と認定補聴器専門店を基準にしましょう。
適切な補聴器を選択できれば、家族や友人と快適な日々を過ごすことにつながります。自分の利用目的や生活環境に合った補聴器を購入しましょう。
参考
独立行政法人国民生活センター 補聴器トラブルを防ぎましょう!
一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 補聴器購入者が医療費控除を受けるために
-
記事投稿者

吉沢仁(よしざわひとし)
看護専門学校を卒業後、病棟看護師として従事する。2021年からWebライターの活動を開始。医療・健康分野を専門にしており、生活習慣病や精神疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、小児疾患などさまざまな分野で執筆経験がある。医療系の総執筆数は200本以上。現在は医療系メディアでSEOライティングを中心に対応中。
-
記事監修者

若山 貴久子 先生
1914年から100年以上の実績「若山医院 眼科耳鼻咽喉科」院長。■詳しいプロフィールを見る■