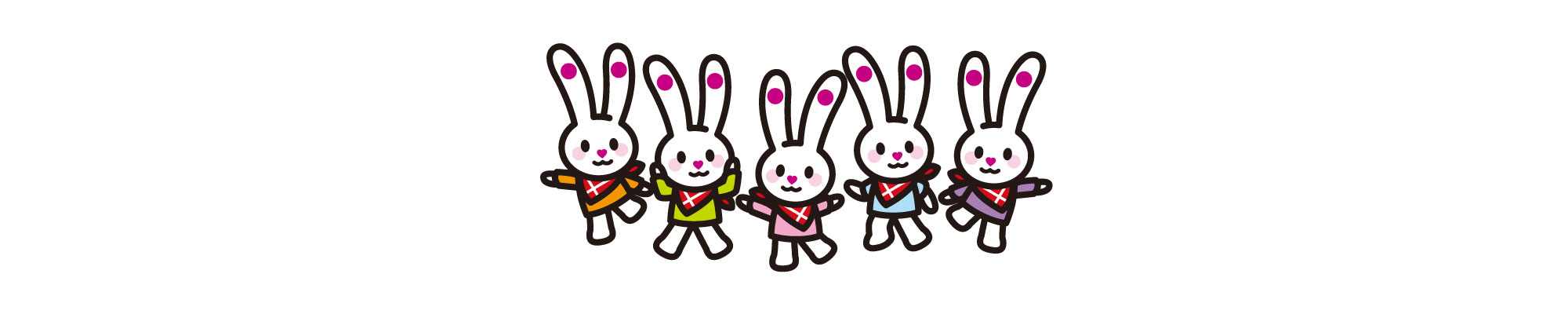「最近親に話しかけると何度も聞き返される」 「電話をしていて会話が通じにくい」 このように感じたことはありませんか?それは聞こえの低下(難聴)が疑われるサインです。難聴はそのまま放っておくと、日常生活においてさまざまなリスクが高まります。本記事では、加齢に伴う難聴の症状やリスク、対処法などについてお伝えします。難聴によるリスクを回避するとともに、周囲とのスムーズなコミュニケーションをとるためにお役立てください。
高齢になると耳が遠くなる人が多い
加齢に伴い聴力は徐々に低下し、40代以降では難聴になる方が増えてきます。このように、加齢以外に特別な原因のない難聴は「加齢性難聴」と呼ばれ、日本全国で1,500万人以上が罹患しているとされています。加齢性難聴の原因と症状について見ていきましょう。
加齢性難聴の原因
加齢性難聴は、耳の中にある聞こえを感知する細胞の減少や変化が原因とされていて、高い音が聞こえにくい、音がひずんで聞こえるなどの特徴があります。細胞自体の変化による症状であるため、加齢性難聴そのものの治療はできません。しかし、難聴の程度に合わせて補聴器を装用するなどといった、聞こえを補うための対処法をとることができます。
関連記事:加齢に伴ってみんな難聴になる?
難聴が疑われる症状
加齢性難聴初期の頃は、「高い音がわずかに聞こえにくい」等の症状に留まることが多く、日常生活への支障は感じにくいかもしれません。しかし、身近にいるご家族が先に気づけることもあるため、難聴が疑われるサインを確認しておきましょう。
- 音は聞こえるが、言葉が聞き取りにくい
- 静かなところでは会話ができるが、騒がしい場所での聞き取りが悪い
- 会話中に聞き返すことが多い
- 後ろから呼ばれても気づかないことがある
- 聞き間違いが増えている
- 話し声が大きい
- 背後から接近する車に気づかない
- 高い音(電子音や家電の音)が聞こえにくい
- 相手の言葉を推測で判断しているふしがある
- ゆっくり話しかけないと聞き取れない
- テレビやラジオの音量が必要以上に大きい
- 耳鳴りがある
- 外出するのが億劫になっている
- 物を置き忘れることが多い(認知症の可能性も含む)
ご家族が高齢になったら普段から聞こえについて気にかけておくとよいでしょう。
難聴を放っておくと生じるリスク

ここからは、難聴によってどのようなリスクが生じるのかについてお伝えします。難聴の症状をそのまま放っておくと、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 認知症発症のリスクが高まる
- 危険察知能力が低下する
- 人との会話など、社会生活に支障をきたす
- 家族や友人とのコミュニケーションが困難になる
- 自信を喪失する
- 鬱状態のリスクが上がる
- 大きな音量でテレビを聴くことで同居者の聴力へも影響する
詳細はこちらの記事をご覧ください。
聴力低下の原因と治療・対処方法|放置すると生じやすいリスクとは?
難聴をそのままにしておくと「聞こえにくい」という耳の症状以外にも、さまざまな悪影響があります。ご本人の聞こえに合わせてテレビなどのボリュームを大きくすることで、同居のご家族の耳にダメージを与える可能性もあります。
そのため、聞こえが気になったら、まずは耳鼻科の受診を促すことが大切です。場合によっては、加齢による難聴ではなく治療ができる難聴の可能性もあります。
また、難聴自体の治療ができない加齢性難聴だとしても、聴力の程度や日常での困りごとから判断して、補聴器の必要性などの相談にのってもらうこともできるでしょう。
加齢による難聴は本人の自覚がないこともある
加齢性難聴はゆっくりと進行するため、ご本人が症状に気づかないことがよくあります。むしろ、周囲の方のほうが、「何度も聞き返される」「テレビのボリュームが大きすぎる」などのサインに先に気づくケースも多いです。
国立長寿医療研究センターによる調査結果では、75~79歳の男性で71.4%、女性で67.3%、80歳以上の男性で84.3%、女性で73.3%が難聴を抱えています。また、日本補聴器工業会が行った調査では、難聴を自覚している人の割合は75歳以上で34.4%にとどまり、自覚者が有病率に比べて大幅に少ないことが分かっています。
実際耳鼻科の現場でも、ご本人は難聴に気づいていなくても、ご家族が異変に気づき受診を促したケースがありました。難聴の症状を放っておくと、認知症などのリスクが高まる可能性があるため、適切な対応が求められます。
ただし難しい点としては、ご本人に難聴の自覚がない場合には、受診を拒むことがあることです。そのような時には、以下の内容を根気よく伝えることが大切です。
- 難聴を自覚できるように丁寧に状況を伝える(テレビの音量が大きい、後ろから声をかけても気づかないなど)
- 治療のメリットを伝える
- 難聴を放置するリスクを伝える
最初は受診を拒まれても、焦らずに少しずつ働きかけることが大切です。また、ご本人が感じる不安や疑問に寄り添いながら、治療やサポートの重要性を伝えていくと良いでしょう。
聞こえにくい親とスムーズなコミュニケーションをとるコツ

聴力が低下した方とのやり取りでは、行き違いや誤解が生じやすくなります。しかし、お互いがその状況を理解し、少し工夫するだけで、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。以下に、そのためのポイントをまとめたので、参考にしてください。
- 【ゆっくりはっきりと話しかける】大声ではなく適度な音量で、口元を見えるようにして、ゆっくりとはっきり話しかけることを心がけましょう。正面から顔を見ながら、マスクを外して話すと、口の動きからも判断しやすくなります。
- 【視覚的な見やすさを活用】手振りや身振り、キーワードを紙に書くなどの視覚的な補助を活用すると、より伝わりやすくなります。
- 【数字や紛らわしい言葉は言い替える】数字の「7」は「しち」と言うと「いち」と聞き間違えることがあります。あえて「なな」と言い替える、文字や指で示すなどして、聞き取りやすい工夫をすることが大切です。
- 【周囲の環境を整える】雑音が多い場所では聞き取りにくいため、テレビなどを消して静かな環境で話しましょう。
これらの工夫を取り入れながら、リラックスした雰囲気で会話を楽しむことが大切です。ゆったりとしたペースでやり取りすることで、聞こえが低下した方でも安心してコミュニケーションを楽しむことができます。ぜひ実践してみてください。
親の耳が遠いと感じたら耳鼻科の受診を促し対策しよう
加齢に伴う難聴は、ゆっくり進行するためご自身では気づきにくいことが多いです。そのため、ご家族の聞こえが低下しているように感じたら、早めに耳鼻科を受診することをおすすめします。適切なタイミングで対策を講じることで、治療の機会を逃さずに済み、難聴に伴う二次的障害を防ぐことができます。
たとえ加齢による難聴で治療が難しい場合でも、補聴器などのサポートツールを活用することで、会話を楽しむことが可能です。家族全員が快適にコミュニケーションをとるためにも、早めの対応を心がけましょう。
参考
広報誌「厚生労働」2024年10月号 特別企画1|厚生労働省
全国高齢難聴者数推計と 10 年後の年齢別難聴発症率―老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)より 内田 育恵、杉浦 彩子、中島 務、安藤富士子、下方 浩史|老年医学会雑誌第49巻2号
難聴高齢者と暮らす配偶者が経験するコミュニケーション上の困難 山田紀代美|日本健康学会誌2022
難聴について | Hear well Enjoy life. – 快聴で人生を楽しく - | 日本耳鼻咽頭科学会
-
記事投稿者

言語聴覚士ライター大井純子
言語聴覚士として病院・訪問でのリハビリに約20年間従事。 「コトバの力で誰かをサポートする」をモットーに、言語聴覚士として働くかたわら、医療記事作成や電子書籍出版サポートなどに取り組んでいる。
-
記事監修者

若山 貴久子 先生
1914年から100年以上の実績「若山医院 眼科耳鼻咽喉科」院長。■詳しいプロフィールを見る■